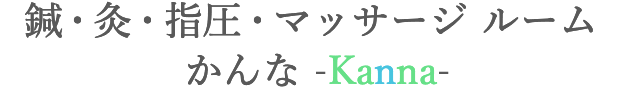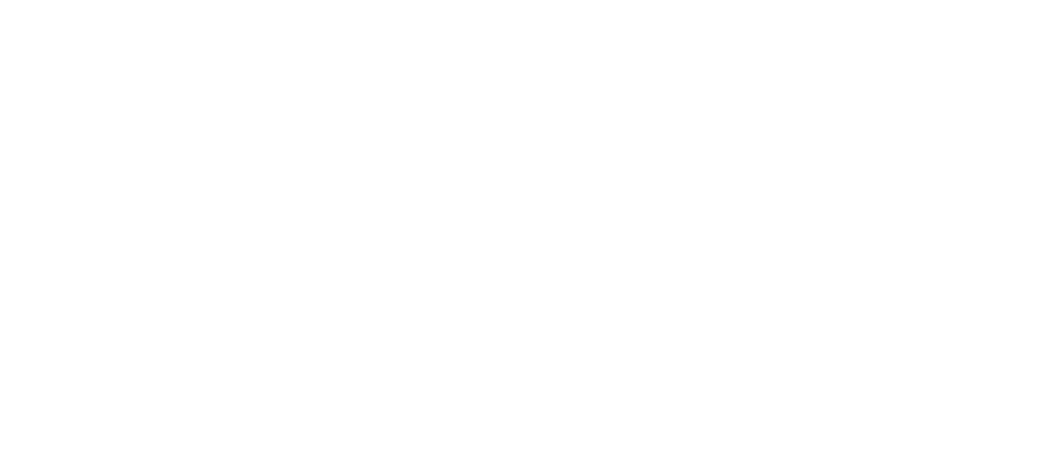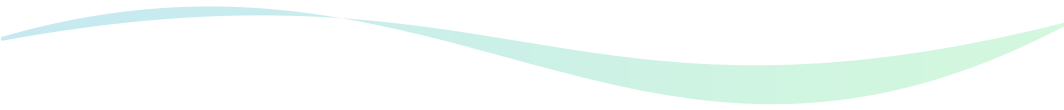これを知ると受けたくなる!秒で効く鍼の〝ひびき〟とは?

鍼は即効性且つ持続性のある治療方法です。
受けた直後のすっきり感と翌日のからだの軽さを体験された方々は、皆さん口を揃えて
「鍼ってすごいね」
と喜ばれます。
痛い、だるい、重い、といった症状が、鍼を刺した瞬間軽減する・・・
そんな魔法にも似た効果が得られるとしたら、興味がわきませんか?
今回は鍼に焦点をあてて、特に〝ひびく〟ことで得られるからだの変化を解説いたします。
目次
- ○ 鍼の種類と方法
- ・鍼にも個性があります
- ・鍼と診断方法
- ○ 鍼が〝響く(ひびく)〟とは?
- ・4つのひびき感
- ・ひびくのを好む人
- ・ひびくのが苦手な人
- ○ 鍼治療を受ける際に注意すべきこと
- ・出血と皮下出血
- ・2つの効果と好転反応
- ・鍼治療の前と後
- ○ 最後に
鍼の種類と方法

鍼やお灸は古代の中国で誕生し、朝鮮半島から日本に伝えられた治療方法です。
中国鍼は鍼自体を持ち、皮膚に差し込むようにして刺します。
日本では主に管鍼法(かんしんほう)という鍼を管に挿入した状態で刺入する方法が主体となっています。
髪の毛程の細いものからボールペンの芯の太さのものまで、鍼の長短も含めるとその種類は多様に富んでいます。
鍼にも個性があります

鍼 イコール 刺す と思いがちですが、その種類と用途は様々です。
簡潔にいうと、「破る鍼」「刺す鍼」「刺さない鍼」の3種類に大別されます。
・破る鍼:皮膚の調和や膿を出す
・刺す鍼:熱や痛み、深部の凝りなどを取り除き、血流を改善する
・刺さない鍼:血流や自律神経を整える
刺す鍼は4種類あり、国内では毫鍼(ごうしん)という鍼が多用されています。
鍼と診断方法

鍼治療に限ったことではありませんが、施術をする前に見るべき4つの診断方法があります。
・望:見る=顔色、姿勢、動作、表情 など
・聞:聞く=呼吸、声色、匂い など
・問:問う=病状や普段の生活習慣などの問診
・切:からだに触れる=脈、腹部 など
上記の四診(ししん)方法をもとに、体外の原因を見極めながら治療を行います。
鍼が〝響く(ひびく)〟とは?

注射針を皮膚に刺す時にチクっとする痛みは『不快な感覚』です。
では〝ひびく〟とは何なのか?
それは気持ちの良さ・安心感といった『心地良い感覚』に結びつきます。
受ける方の体質や感性で得られる反応も異なりますので、パターン別にご説明いたします。
4つのひびき感
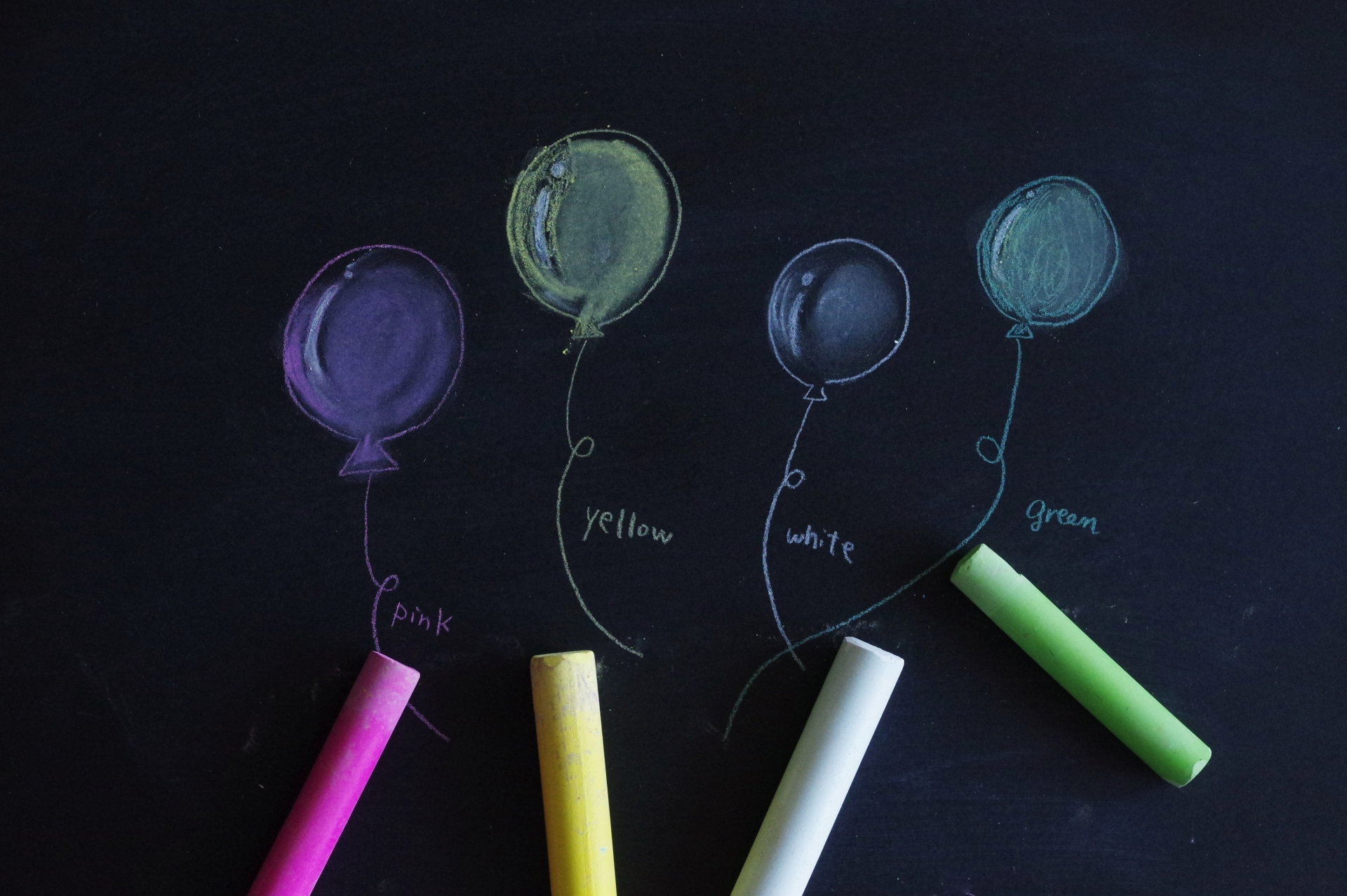
鍼は刺した後に、上下に動かす、回す、弾くなどの手技を加える事で、
患部に「ズンとひびく」または「びりっとする」ような感じを得られます。
この刺激の事を「ひびき(響き)」といいます。
このひびきは「得気(とっき)」ともいわれており、
気血の流れが良くなる独特な感覚です。
ひびき(得気)感は主に以下の4種類があるといわれています。
・酸(さん):だるさ
・麻(ま) :しびれ
・重(じゅう):圧迫感、重さ
・腫(ちょう):張り感、腫れぼったさ
例えば慢性的な腰や肩の痛みがある場合、
硬くなった筋肉が神経を圧迫
↓
その箇所に鍼を刺すことで体内の免疫細胞が異物と判断
↓
無意識に身体を守ろうと活性化する為、一時的に筋肉が収縮
このような経緯のもと、圧迫されている神経を鍼の刺激によって起こる筋肉の防御反応を利用することで更に圧迫するため、その際にズーンと重く感じたり、ビリっと感じたりします。
これがひびきのメカニズムとなります。
ひびくのを好む人

鍼のひびきを好む人は、鍼を受け慣れていたり、ひびいた後の症状の改善を体感されている場合が多いです。
「ズーン」「ドーン」という感覚の直後に患部が温かくなったり、じんわりと浸透しているようだと表現されることもあります。
ひびくのが苦手な人

鍼治療を受けられるのが初めての方や、鍼に対して恐怖心を持っている方は、
大小なりとも緊張状態であるが故に筋肉が硬くなりやすく、鍼などの外部刺激にも敏感になりやすくなっています。
その為、ひびきを不快・違和感ととらえる場合もあり、患部や気血の巡りが良くなっても緊張感が緩まなくては効果は半減してしまいます。
鍼の刺激に抵抗なく慣れるまでは、刺激量を調整(細い鍼を使用、本数を少なく、短時間など)して受けることが望まれます。
鍼治療を受ける際に注意すべきこと
出血と皮下出血
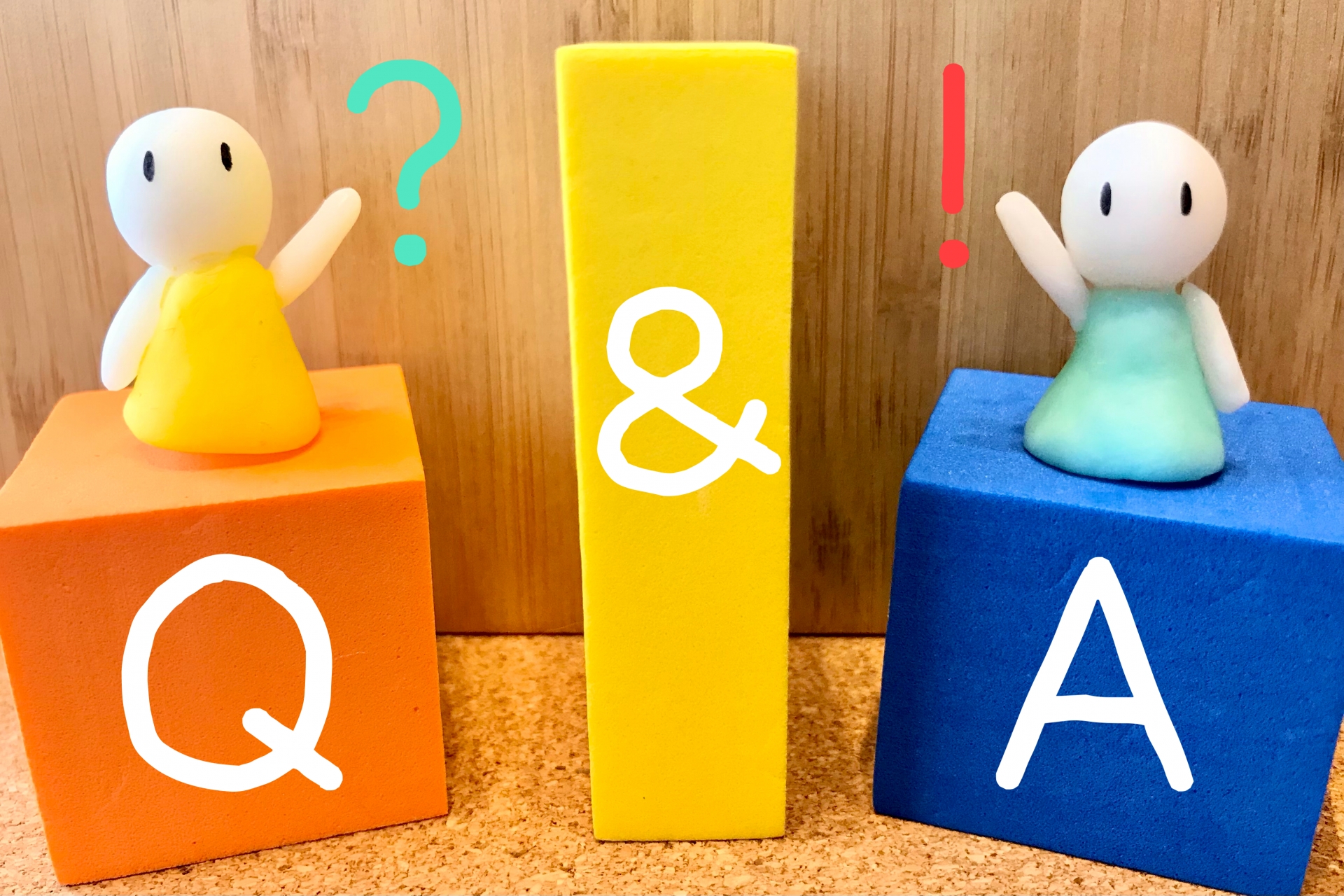
鍼の施術では、常に細心の注意を払っていても皮下出血やごくわずかな出血を伴う可能性をゼロにすることはできませんが、身体への悪影響はありません。
稀に青あざが生じる場合でも、個人差により1〜2週間で自然に退消します。
2つの効果と好転反応

鍼(灸)治療は施術後すぐに反応が出る直後効果と、翌日から数日にかけて現れる事後効果があります。
好転反応とは、施術を受けた際に身体が回復へ向かう際に起こる反応で、全ての方に起こるわけではありません。
一時的な怠さや強い眠気の他、発汗やかゆみ、発熱、下痢など、症状や程度は個人差があります。
一見不快な症状ともいえますが、気血の巡りがスムーズになるが故のからだの変化ですので、睡眠を十分にとることで良くなります。
鍼治療の前と後

治療前後1~2時間は食事や入浴、激しい運動は控えてください。
発熱時や飲酒時は施術をすることができません。
尚、血液循環や代謝を高めるため、施術後の飲酒はいつもより酔いやすい状態となりますのでご注意ください。
最後に

体表からの刺激であるマッサージやお灸とは対照的に、鍼は一時的に体内へと入って刺激を与える独自の療法です。
ひびくことで痛みがとれる即効性と、定期的な治療で根本から体質を改善できる持続性は、
人が本来持っている自然治癒力を高めてくれる心強いサポーターともいえます。
興味を持たれた方は、安心感や幸福感によって自然と体温が上がる豊かなひと時を
どうぞご体感ください。
鍼灸と指圧の相乗効果に関しては↓こちらのブログをご覧ください。