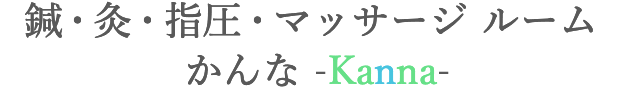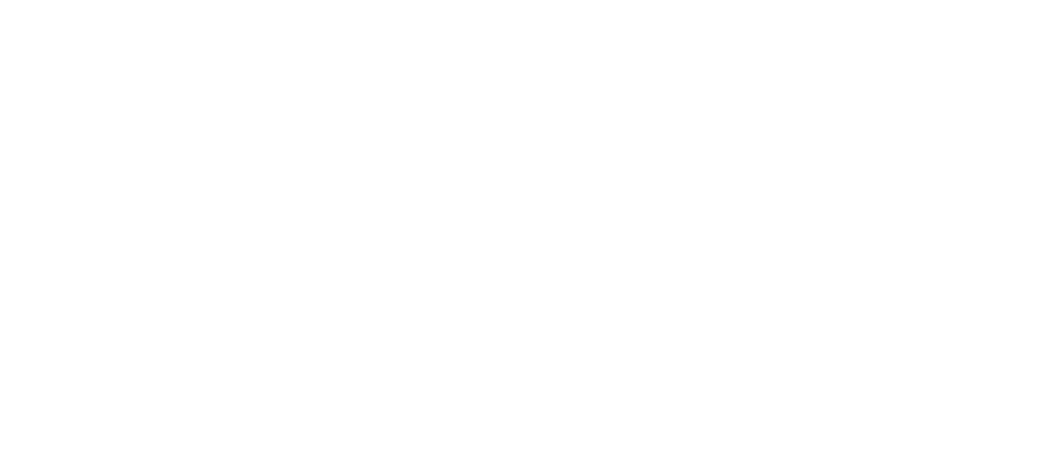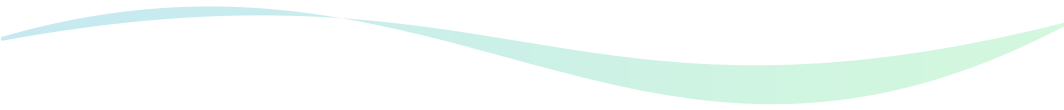自然に還ると健康になる!リラックスする為の必須条件とは?

リラックス状態の時、私たちは自然と深い呼吸ができています。
心と体の両方を休めることができる方法は多様にあり、指圧やマッサージもその手段のひとつです。
近年の疾病の影響による過剰な程のマスクや消毒を強いられている状況は不自然そのものであり、
心身へは想像以上に負担がかかっています。
今一度、ご自身の体調や環境を見直して、より良い状態を保てる情報源となります様、
リラックスの効果や方法を解説いたします。
目次
- ○ ストレスとリラックス
- ・緊張状態の脳と体
- ・弛緩状態の脳と体
- ○ リラックスする為に意識したいこと
- ・五感とは
- ・五感の優先順位と感覚タイプ
- ○ 〝今ココ〟でできるリラックス方法
- ・触覚・聴覚・視覚
- ・嗅覚・味覚
- ○ 最後に
ストレスとリラックス
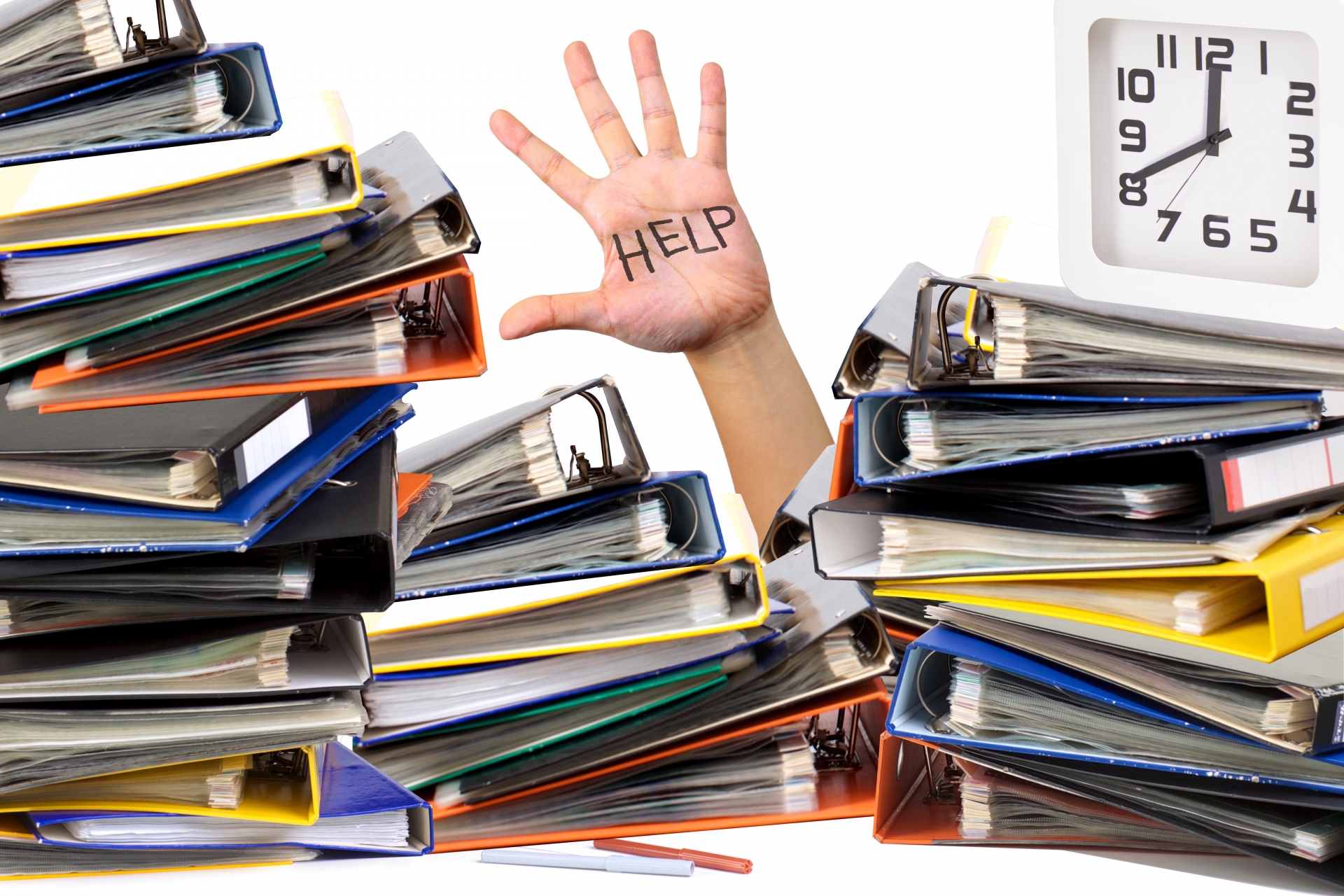
朝起きて活動する時と夜寝る前の時では、肉体的にも精神的にも大きな違いがあります。
ストレス状態は『緊張』、リラックス状態は『弛緩』とも表現することができます。
両方のバランスが程良く保たれていることで、日々の健康維持やパフォーマンスの向上へと繋がります。
緊張状態の脳と体
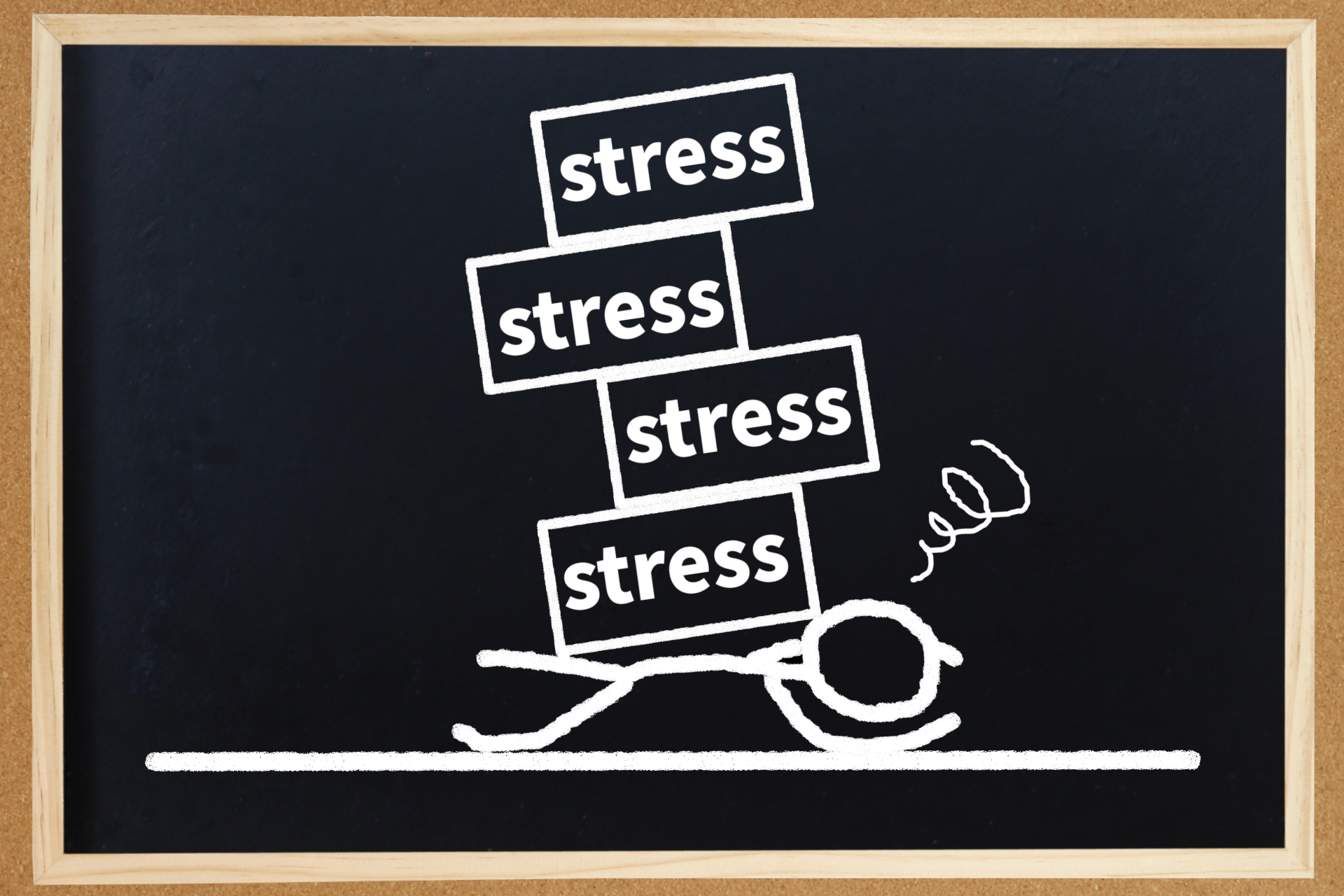
ストレスには以下の3つの段階があると言われています。
①警告反応期:ストレスに対して身体が反応
②抵抗期:外界からの刺激や負荷(=ストレッサー)に抵抗しつつ身体の機能を維持
③疲弊期:抵抗力が限界をむかえる
これらは「ストレス反応」と呼ばれ、人間関係や家庭、仕事などの精神的刺激だけでなく、
気候の変動や気温の変化による身体的刺激に対する心身の反応が、様々なストレス性の症状として現れます。
具体的に言うと、
不眠・胃腸障害・肩こり・めまい・便秘・下痢・蕁麻疹・集中力の低下・抑うつ感
などがあげられます。
弛緩状態の脳と体

緊張とは反対に、弛緩=リラックス状態の時は、くつろいだ、ゆったりとした気分になります。
筋肉が緩んで、無意識のうちに深くゆっくりとした呼吸ができる為、血中の酸素濃度も上がって血行が良くなります。
近年ではこうしたリラックス状態の時に免疫力が高まると言われ、「リラクゼーション」という言葉も今では馴染み深いものになっています。
リラックスする為に意識したいこと

リラックスする方法は様々ですが、好みや向き不向きは個々で異なります。
心と身体を健やかに保つ為には、特に脳疲労をためないようにすることが重要です。
私たちの身体に備わっている「五感」という視点から、リラックスする為のポイントを解説いたします。
五感とは

①視覚(見る)
②聴覚(聴く)
③味覚(味わう)
④嗅覚(嗅ぐ)
⑤触覚(皮膚で感じる)
以上の5つの感覚を五感といいます。
脳はこれらから得られた情報をもとに、肉体や精神に指令を出して私たちの体調をコントロールしています。
五感の優先順位と感覚タイプ

五感には活用しやすい優先順位があります。
「触覚」>「聴覚」>「視覚」>「嗅覚」>「味覚」
個人差により、特に上位3つの「触覚」、「聴覚」、「視覚」のタイプに分けることもできます。
(※感覚タイプが同じ人とは波長が合いやすい)
〝今ココ〟でできるリラックス方法
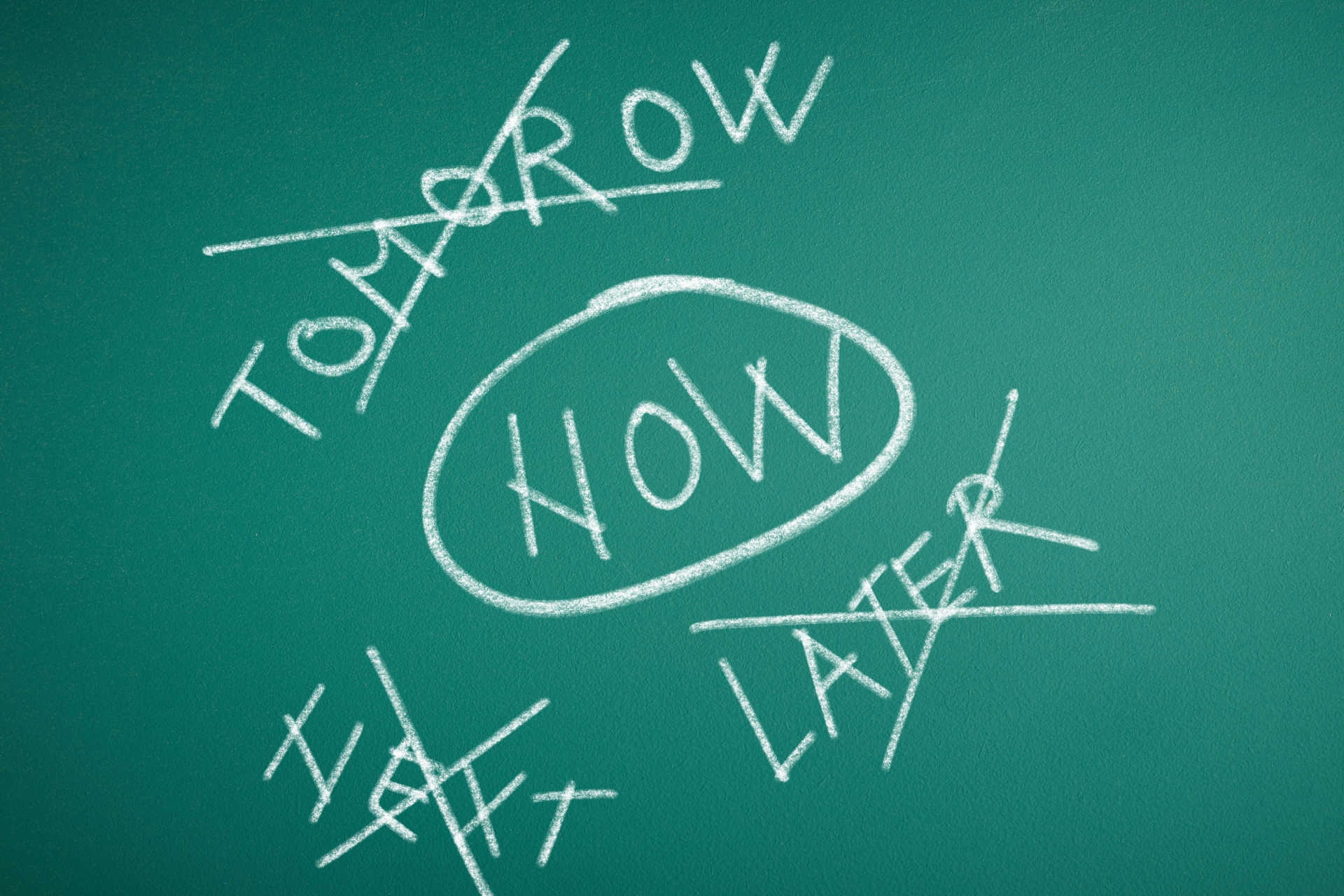
日々膨大な情報を見たり聞いたりしていると、脳は知らないうちに五感を鈍くしてパンクしないように防ぐ働きをすると言われています。
簡単な行動であれば、脳は約21日間で慣れていき、やがて習慣化します。
日常のふとした時にできる五感を刺激したリラックス方法をご紹介いたします。
触覚・聴覚・視覚

触覚:温かいものに触れる・マッサージ(特に頭皮)・ストレッチ・ゆっくり入浴
聴覚:好きな音楽を聴く・流水や鳥の声を聴く
視覚:遠い景色や空を見る・絵を描く・好きな動物の動画や写真を見る
嗅覚・味覚

嗅覚:アロマオイルの香りを嗅ぐ(植物性なので粒子が細かく、香水などよりも脳を刺激しやすい)
味覚:旬の味覚を取り入れつつ、好きなものを快く食べる
最後に

普段は何も思わずに生活していても、ふとした体調不良や違和感を感じた時に、本来の健康な状態が何なのかがわかることがあります。
心も身体も「これが当たり前」ということは存在しません。
不調な時にどう手当をするかで、私たちのからだは多くの発見や可能性を見出すことができます。
今回の記事も、思い立った時にどうぞお役立てください。
読んで頂きありがとうございました。